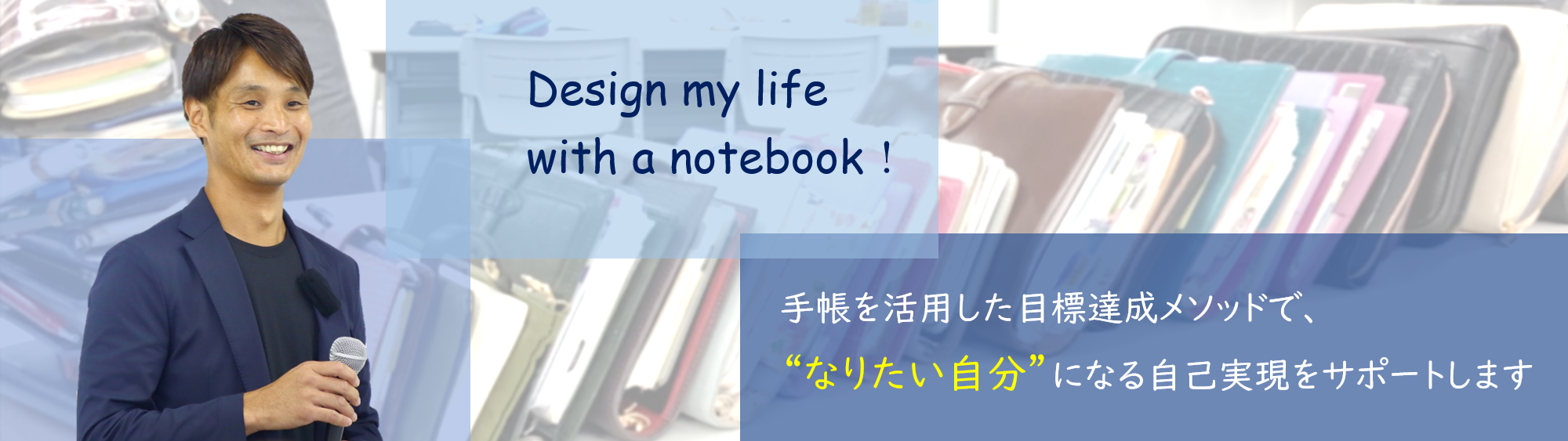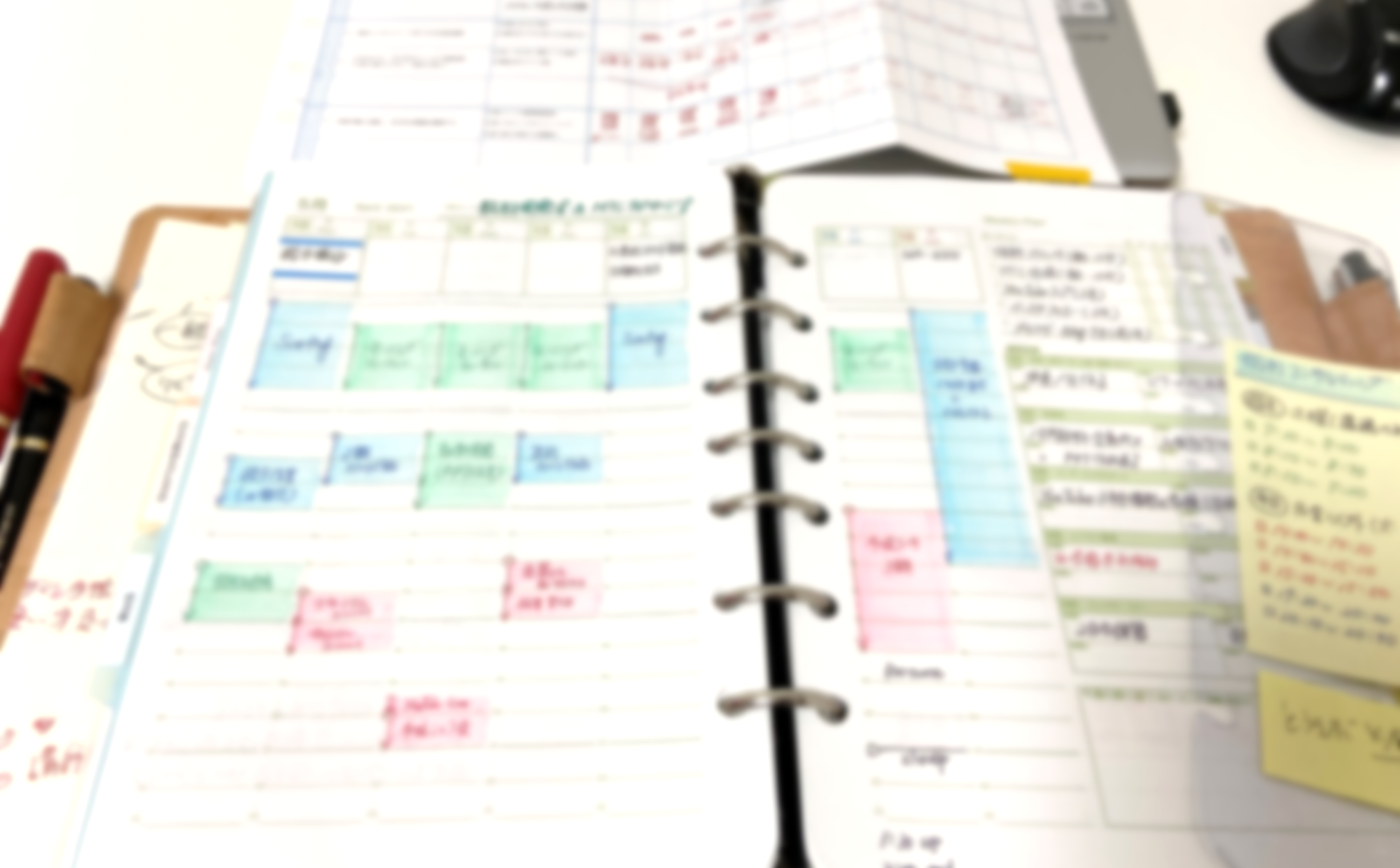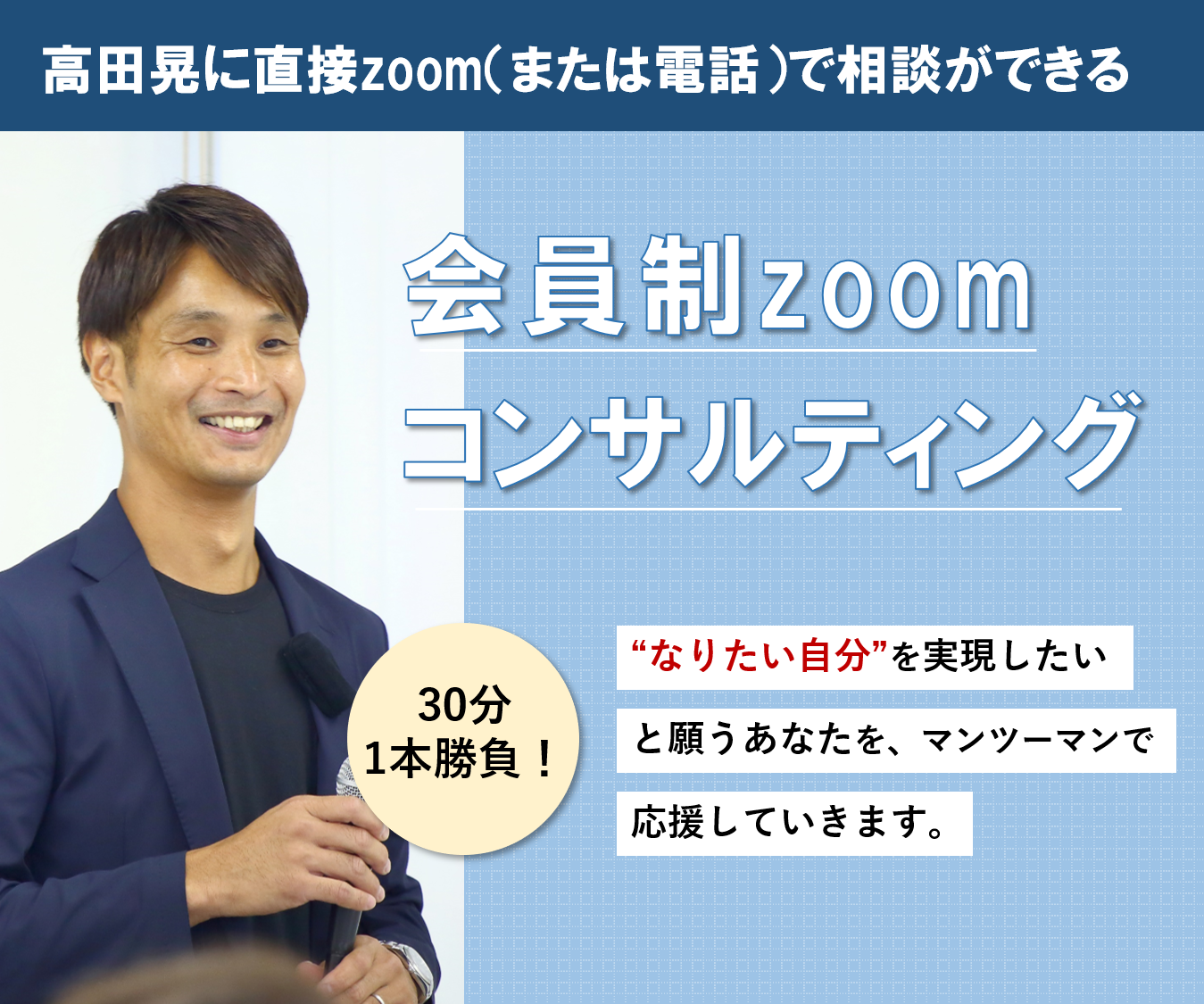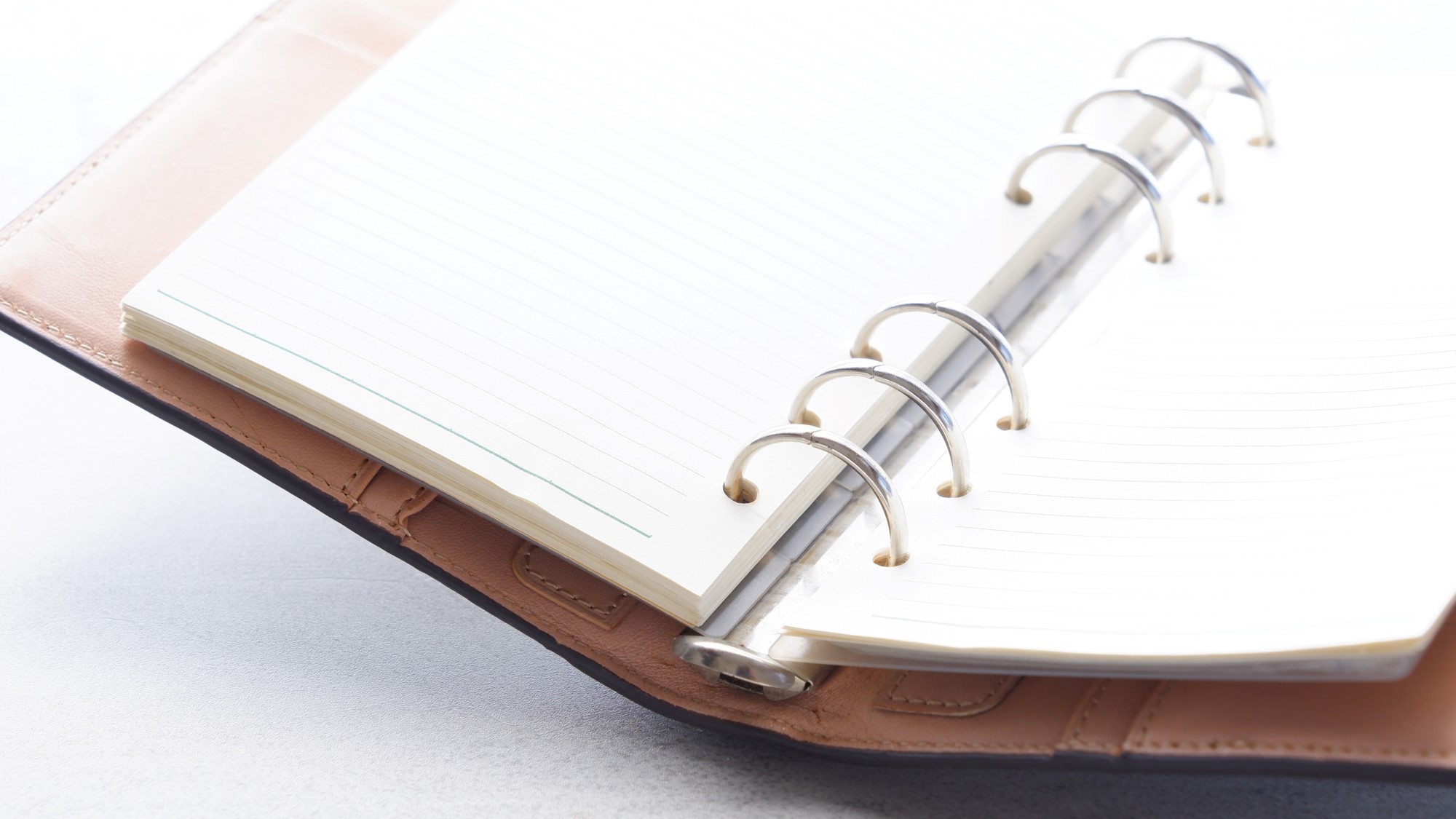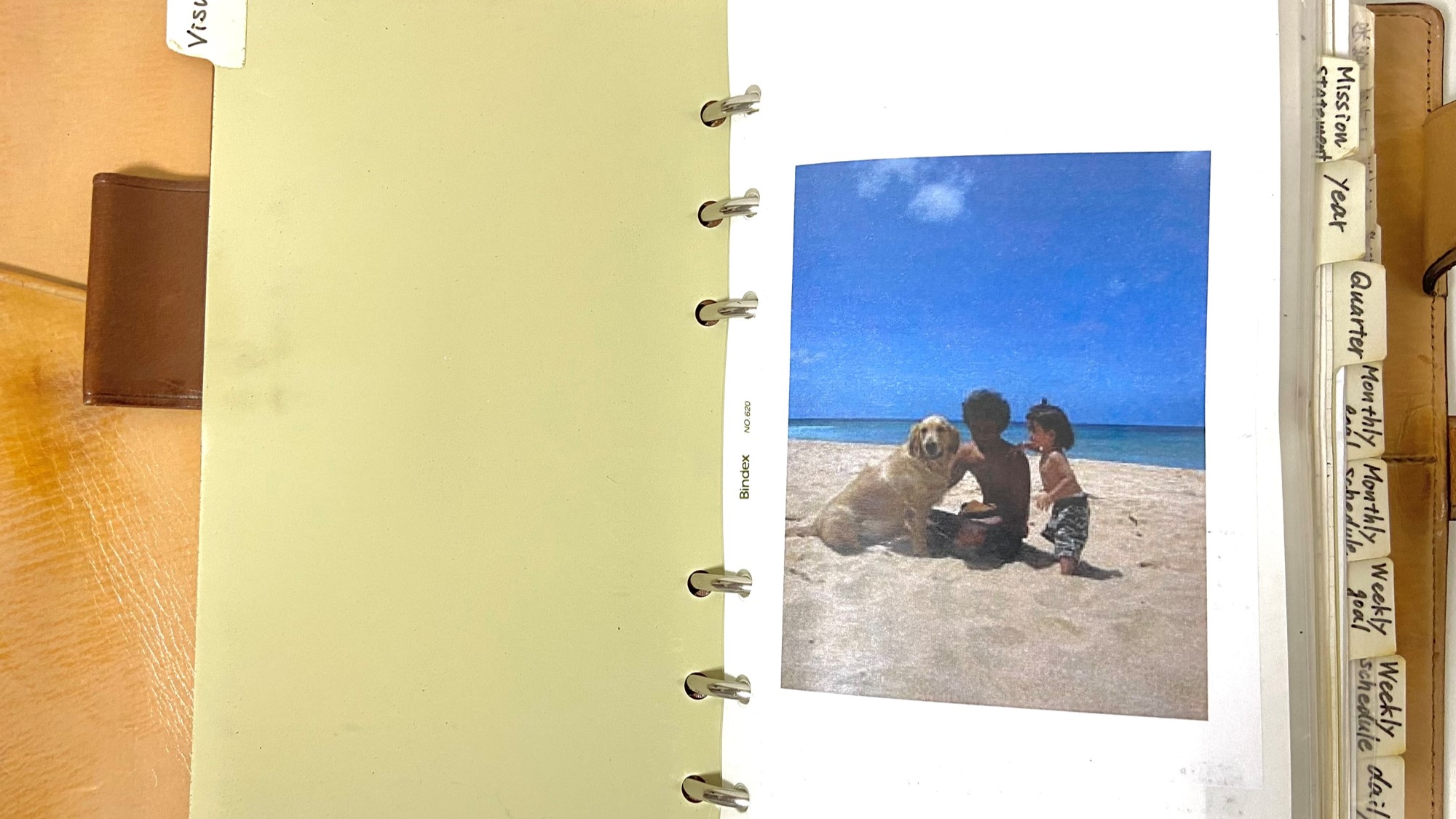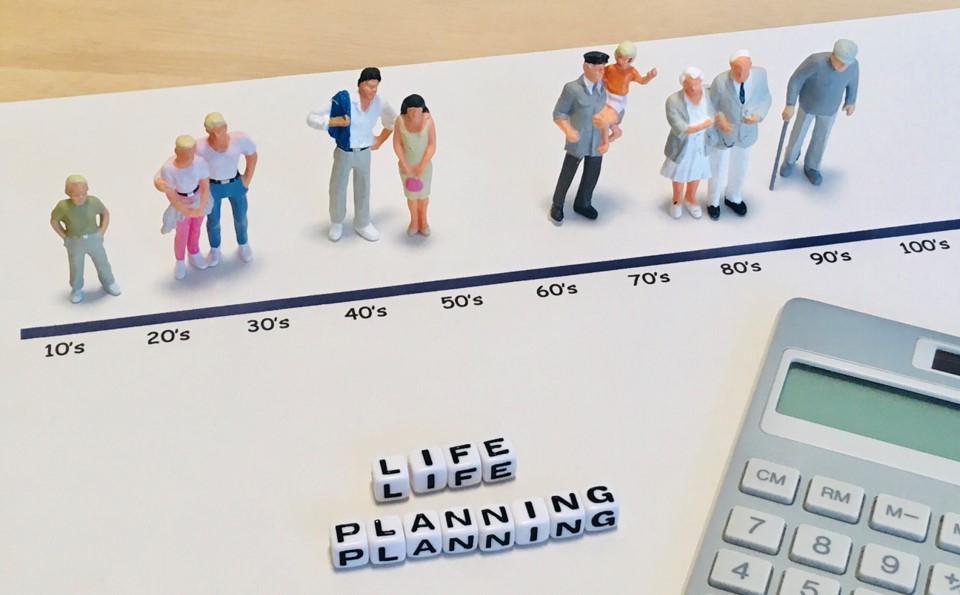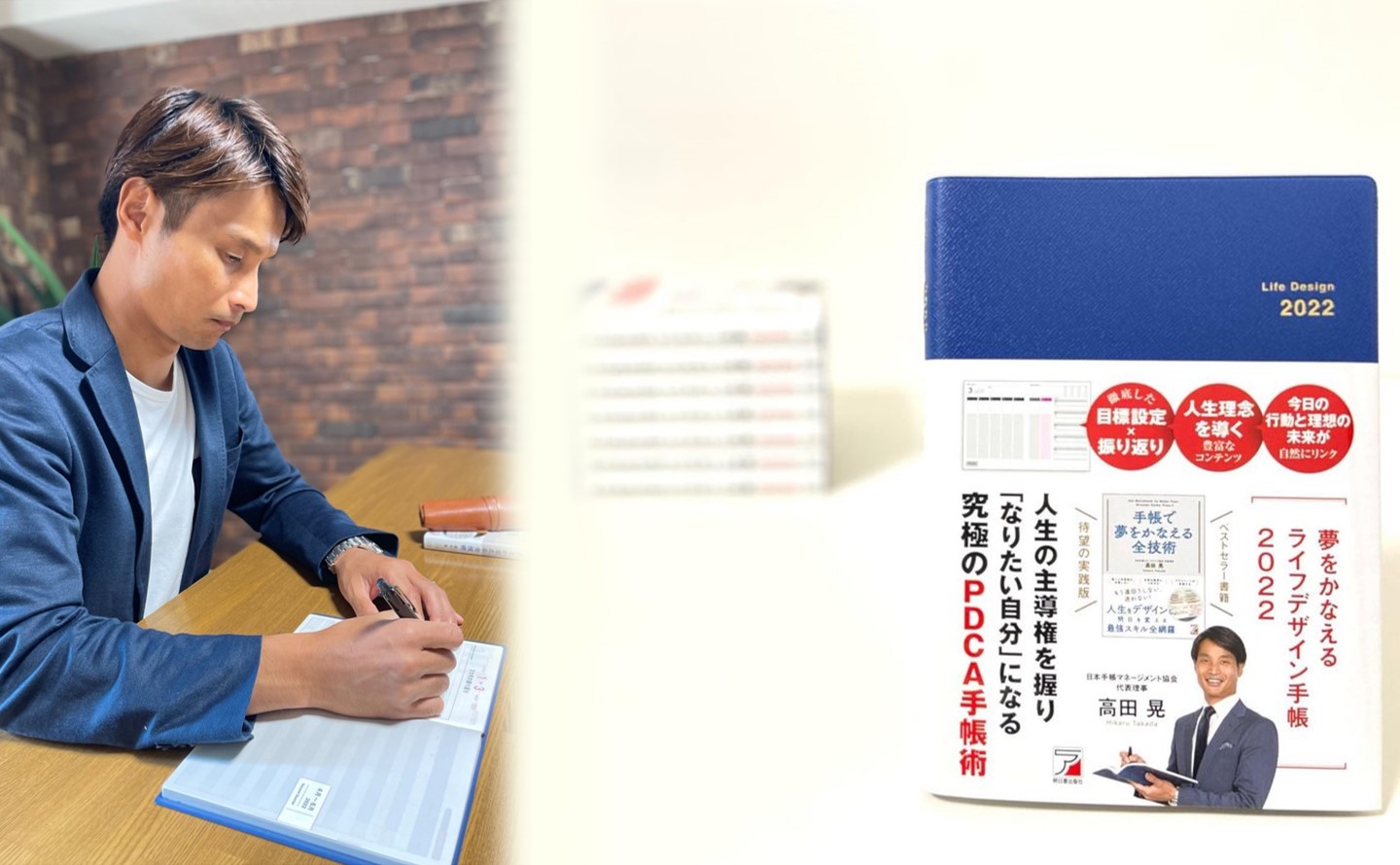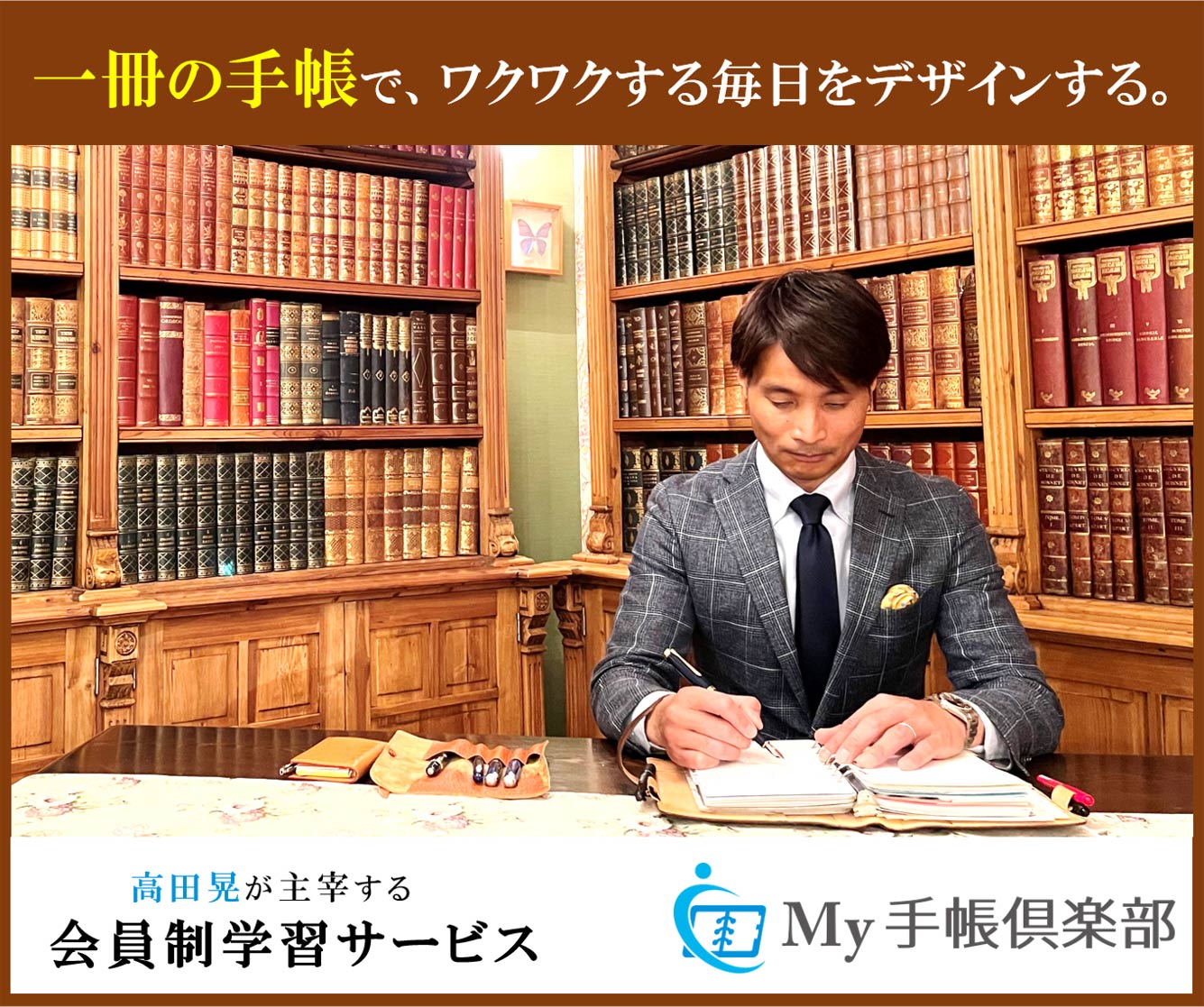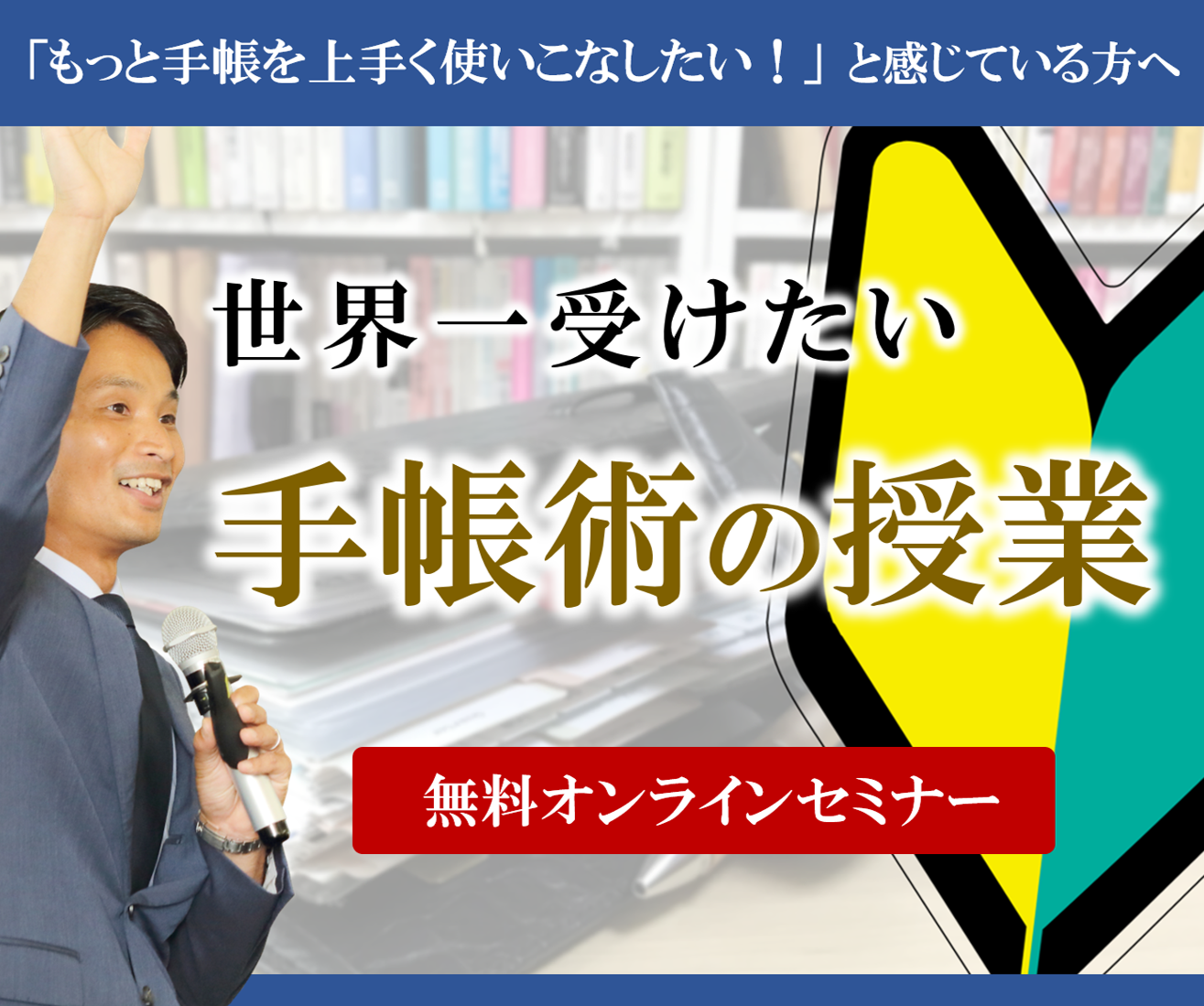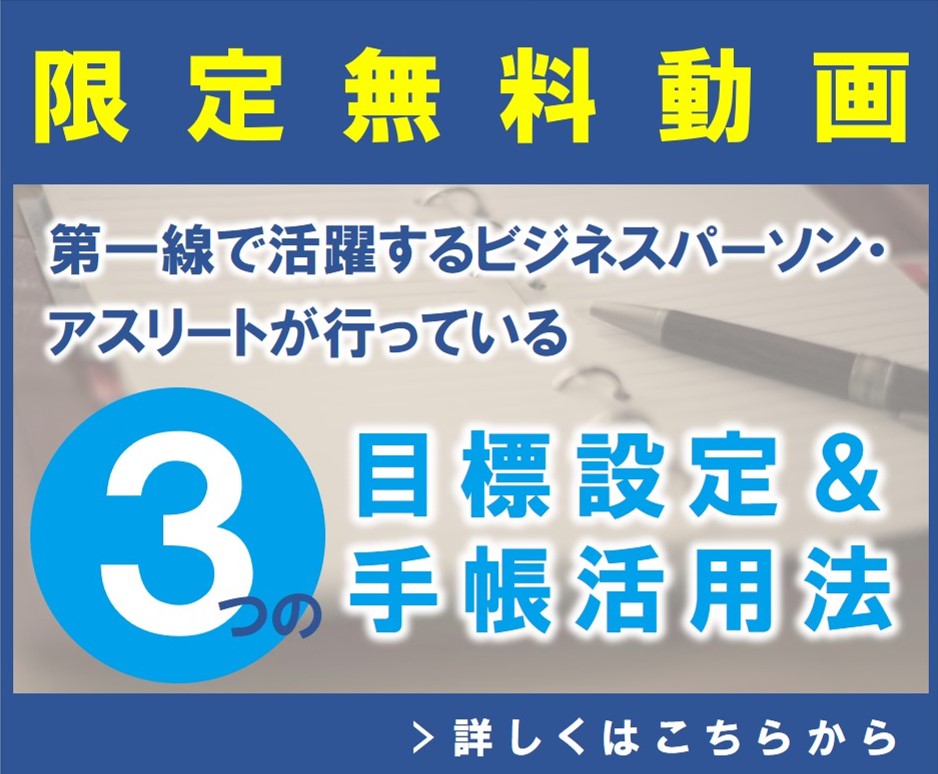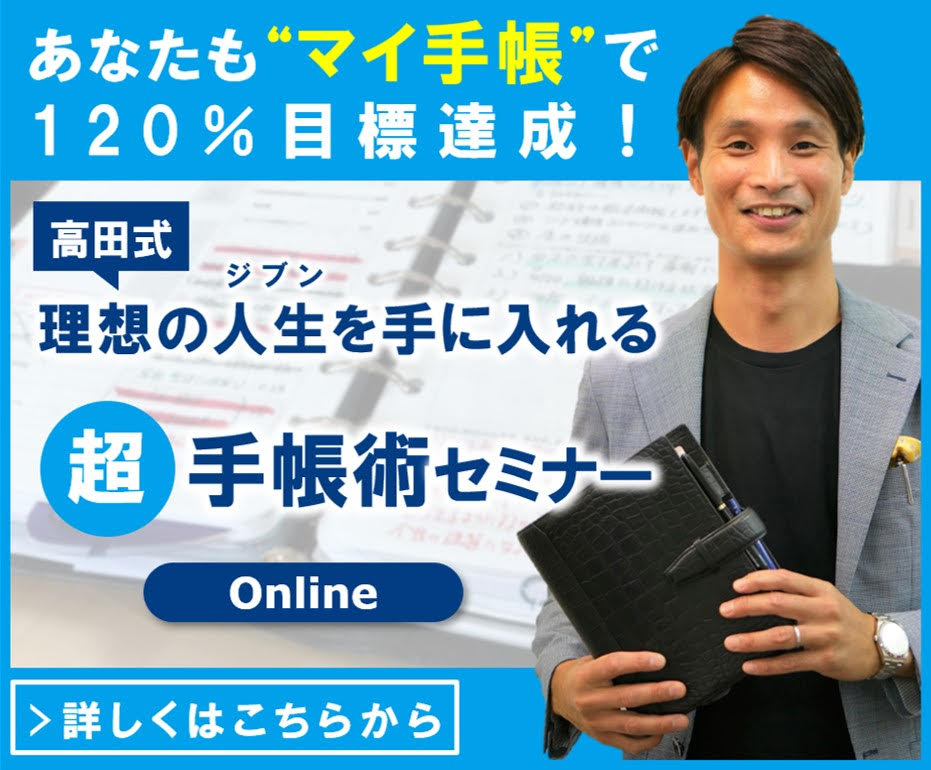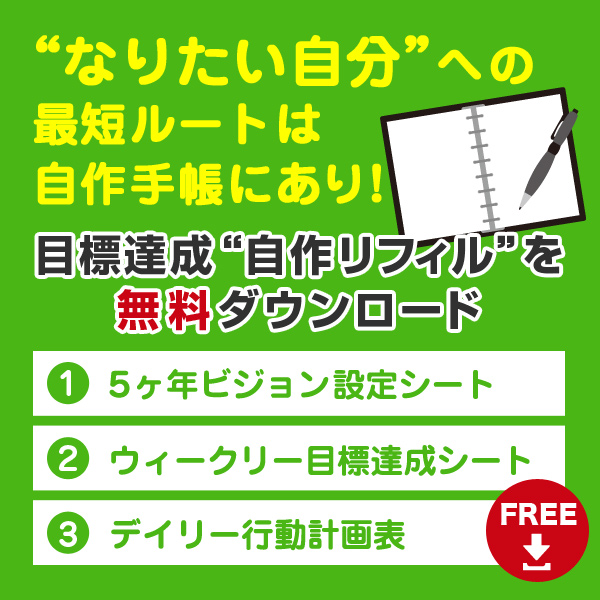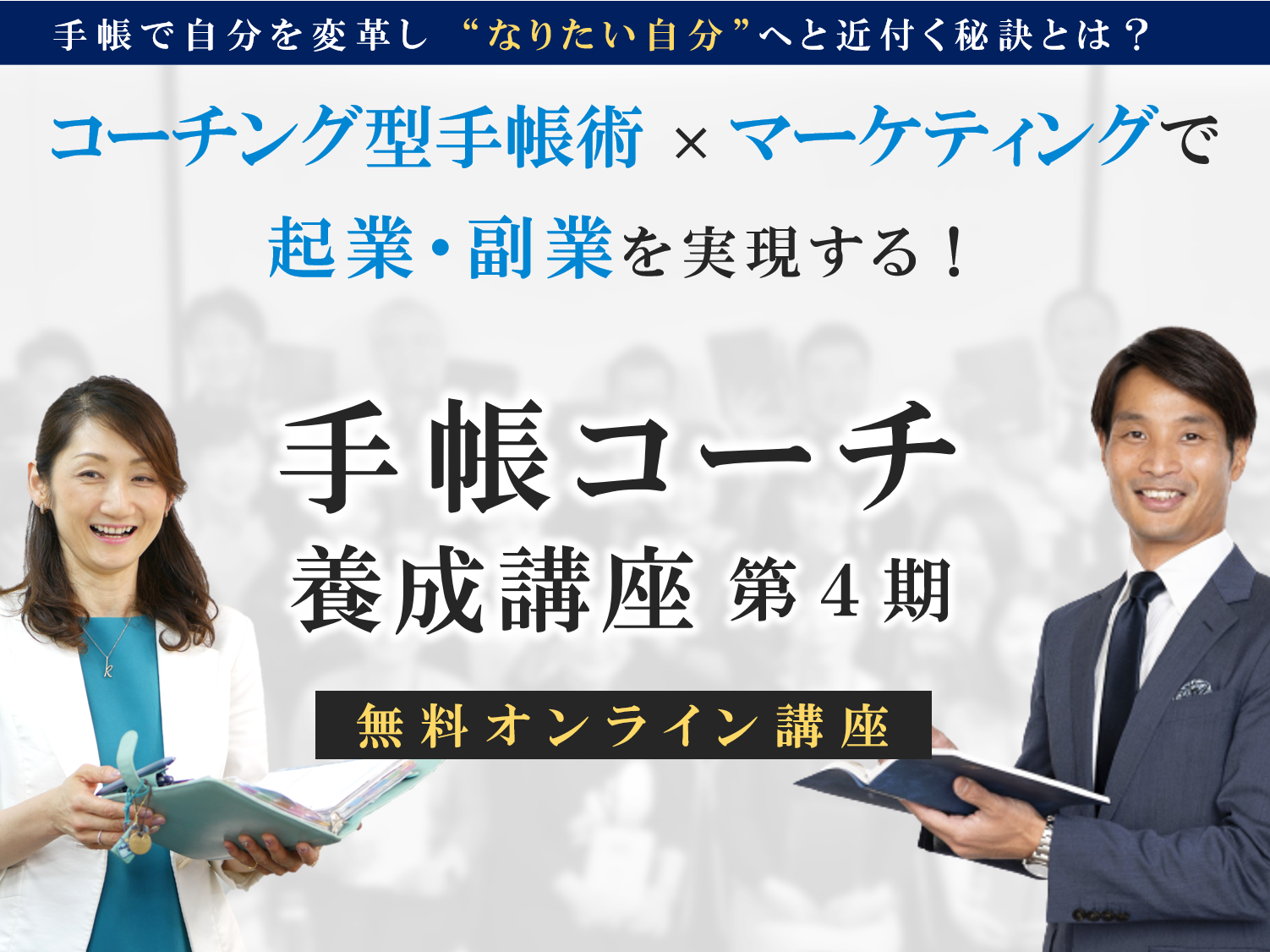こんにちは、高田です。
先日、ある方が「私は計画を一切立てません!」と言っていました。
その理由をよくよく聞くと、「セレンディピティを大切にする」ために計画は立てないと。
そもそも、セレンディピティとは?
セレンディピティとは素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見することを指します。
一言でいうと、「ポジティブな偶然」といったところでしょうか。
高田の記憶では、2007年頃に発売された勝間和代さんのご著書でこの言葉が使われて以来、わりと世間一般の方の間でも使われる言葉になったような気がします。
「こんな人と会えたらな・・・」
なんて思っている時に、偶然ドンピシャな人に出会う、みたいな。
冒頭の人によると、「起こった出来事、出会いの中でもっとも良いものを選択していくのが一番良い」。
だから、私は計画を立てません、と。
確かにこういうタイプの人はいます。
目標を決めるのではなく、その場その場で臨機応変に対応していくタイプ。
これで上手くいく方が存在しているのも確かです。
しかし、よくよくちゃんと観てみると、実はそういう人でも、やっぱり大まかな方向性は持ってるんですよね。
で、その方向性に対して、「こういう人との出会いはないか?」「こういう商品がないか?」といった形で、一種のアンテナが立っている。
アンテナが立つから、偶然の出来事が自分の意識に引っかかるし、目に留まる。
実際、この人に聞いてみると意外とやりたいことが明確でした。
その人が不要という計画が、その人の頭の中ではしっかり描かれていたのです(笑)
「計画不要論」が存在する理由
稀に「計画不要論」を説く人がいますが、その主張の本質をじっくり聞くと、けっきょく言っていることは「紙に細かく書いたものが不要」って言ってるだけなんです。
つまり、本質的には計画そのものを不要といっている訳ではない。
でも、こういうのを聞くと、その上っ面の表現から「あ、計画って立てなくてもいいんだ!」と表面的に誤った解釈をしてしまう人が出てきてしまうから、厄介だったりします。
「計画を立てる」ことの本質
ここまでのお話から、高田が提唱する「計画を持つこと」の妥当性を強く主張したいのだと感じられたかもしれません。
しかし、あくまで計画を立てる行為そのものは手段でしかない。
つまり、どっちでもいいんです(笑)
計画を緻密に立てようが、セレンディピティ優先で、「場当たり成り行き人生」にしようが、自分が今の生き方や結果に、満足感や幸福感を感じられているのであればどちらでもよい訳です。
但し、「自分が目指しているもの」に対して一歩一歩近付いていく。
その努力を重ねるプロセスそのものに、人は手応えや満足感、幸せを感じたりするのも確かです。
そういう意味においては、やはり私は大まかであっても計画という名の「羅針盤」を持つべきと考えます。
ただ一方で、あえて「羅針盤を持たずに航海に出る」というハラハラ・ドキドキする出たとこ勝負のような選択もありかもしれません。
高田